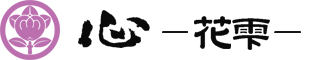![]()
花魁道中について

高下駄を履いた花魁の華やかな歩みは、花魁道中として周囲の注目を集める。
高下駄を履いた花魁の華やかな歩みは、花魁道中として周囲の注目を集める。
![]()
京都島原「太夫の道中」

花魁道中は、客に招かれた太夫(たゆう)が妓楼(ぎろう)から揚屋(あげや)へ移動する「揚屋入り」から始まります。この太夫の移動の行列を 「太夫の道中」 と呼びます。
揚屋とは、客が上流の遊女を呼んで遊ぶお店のことです。客が馴染みの太夫を指名すると、揚屋から妓楼にいる太夫へ連絡が入り、太夫は迎えに出かけます。
この際、太夫は以下の人々を連れて歩きます。
引舟女郎:1〜2人
禿(かむろ):1〜3人
下男:1人
やがて、太夫たちはより豪華で美しく見せるために装いを競うようになり、その道中は人気の太夫を見ようとする人々で大変賑わったといいます。
一方、妓楼とは遊女を置き、客をもてなす店のことです。規模によって 大見世・中見世・小見世 に分かれ、それぞれ遊女の揚代も異なっていました。唯一公に許可されていた吉原は、他の岡場所に比べて格式が高い場所とされていました。
![]()
江戸吉原「花魁道中」
江戸吉原では、客がお座敷で引手茶屋(ひきてぢゃや)や揚屋で宴の時間を楽しんでいる間に、花魁が客の待つ揚屋へ向かいます。揚屋への移動には、約18cmもある黒塗りの三枚歯下駄を履き、歩く際に八の字を描くように進みます。この移動のことを 「花魁道中」 と呼び、八文字の歩き方こそが花魁道中の象徴的なイメージです。
八文字の歩き方には、京都で行われていた 内八文字 と、江戸吉原で広まった 外八文字 の二種類があります。
内八文字
足を前に出す際に内側に踏み出し、円を描くように美しい曲線で歩きます。内側に向かって進む歩き方は、上品でおしとやかな印象を与えます。
外八文字
内八文字に比べ、足を外側に踏み出す歩き方です。動きが大きく、色気や華やかさを表現するのに適しており、江戸吉原の花魁道中ではこちらが主流となりました。