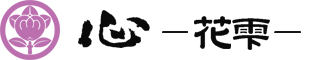![]()
花魁の化粧 白

花魁とは、江戸時代における吉原遊廓の遊女で位の高い者のことを言い、
その時代の女性達のいわゆるファッションリーダー的存在であったとされています。
花魁とは、江戸時代における吉原遊廓の遊女で位の高い者のことを言い、
その時代の女性達のいわゆるファッションリーダー的存在であったとされています。
![]()
当時の花魁のお化粧事情
日本でも古くから化粧の習慣がありましたが、主に貴族などの特権階級の人たちのものでした。一般庶民の人たちの化粧が一般的になったのは江戸時代のことで、その頃から花魁や人気歌舞伎役者のメイクを真似したり、高価な化粧品に代わるメイク法を生み出したりしていたようです。化粧品の溢れる現代に生きる私たちは恵まれていますね。江戸時代における花魁(江戸美人)メイクですが、特徴としては「白・黒・紅」が三色美とされており、白い肌と黒い髪、それを彩るように小さく入れる紅が美人の象徴でした。

![]()
美に対してストイックな花魁達
今回は三色美の中の「白」をテーマにお話しします。
かつて女性は、肌の白さこそ美しさの象徴とされていました。水で溶いた白粉は顔だけでなく、首や襟足、肩、胸元まで塗るのが常識で、「色の白きは七難隠す」という言葉もこの頃から存在します。白粉の濃淡で肌の質感や顔の立体感を表現していたそうです。
1692年発行の『女重宝記』には、「女と生まれては一日も白粉を塗らず顔に有るべからず」「毎日欠かさず白粉を塗り、家人が起きるまでに髪を整え、お歯黒をし、身支度を整えるべし」と記されており、当時の女性は寝るまで化粧を落とさない人も多く、入浴中も化粧をしていたことがあったほどです。現代のように日焼け止めやファンデーションが無い時代、白粉は美肌のために欠かせない存在でした。
また地域差もあり、江戸では薄化粧、京坂では古風な濃い化粧が好まれました。現在、京都ココログループには海外のお客様も多く来店されますが、美人の基準の違いに驚かされることもあります。もしかすると、いつか白粉ブームが再び訪れるかもしれません。